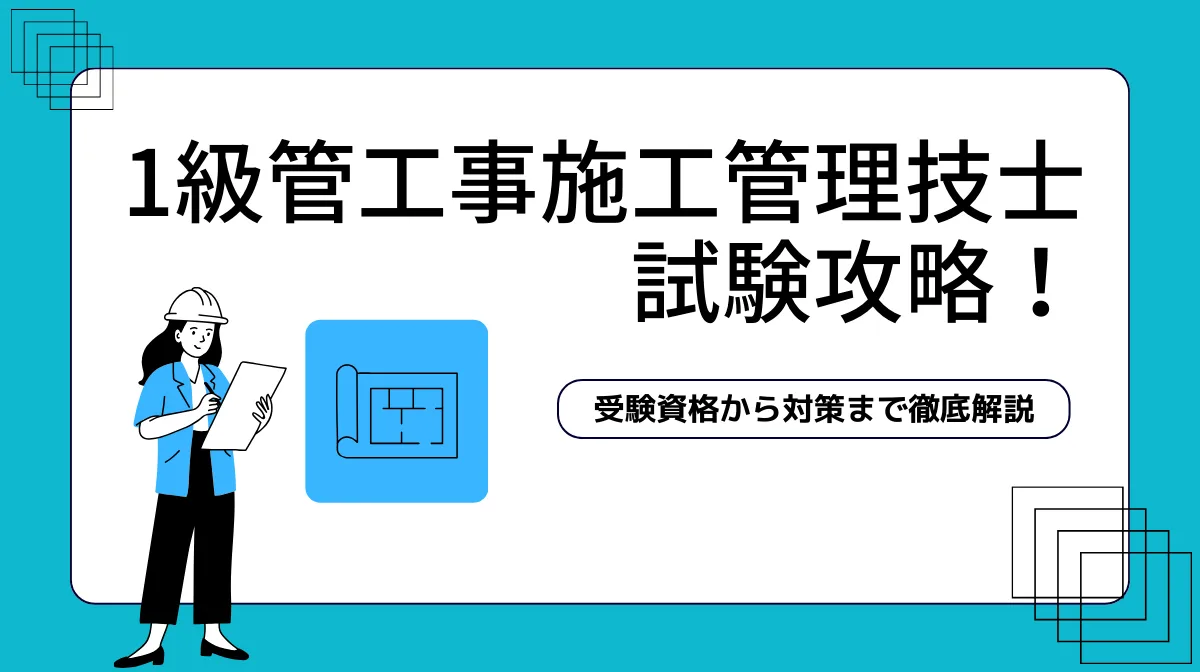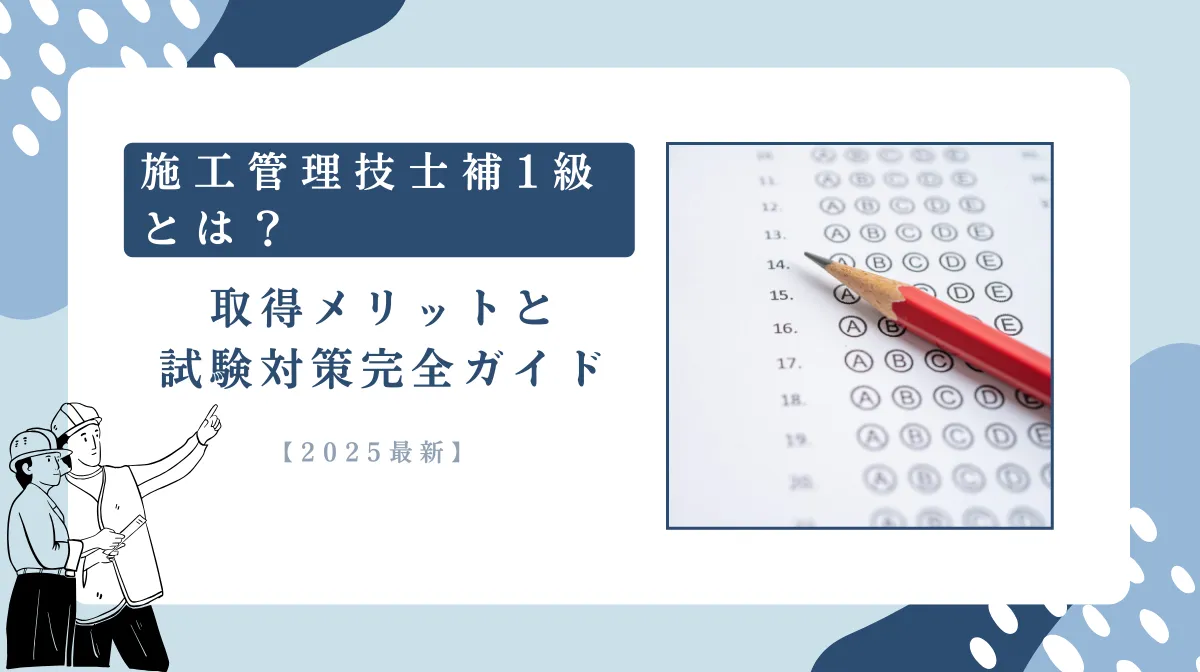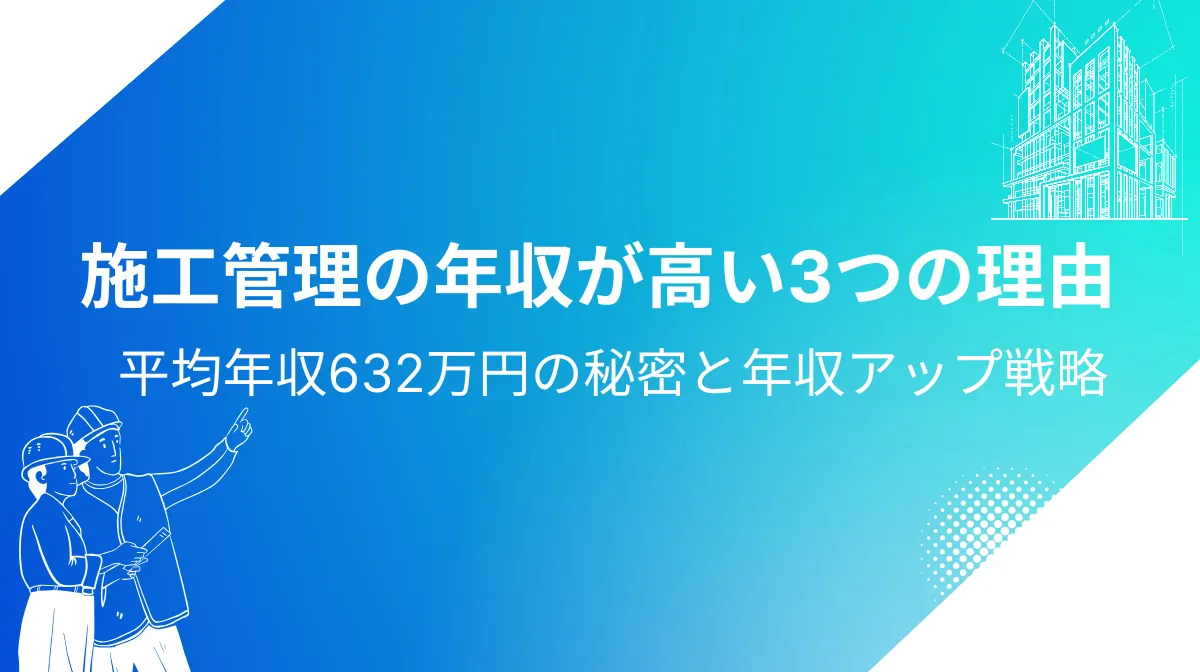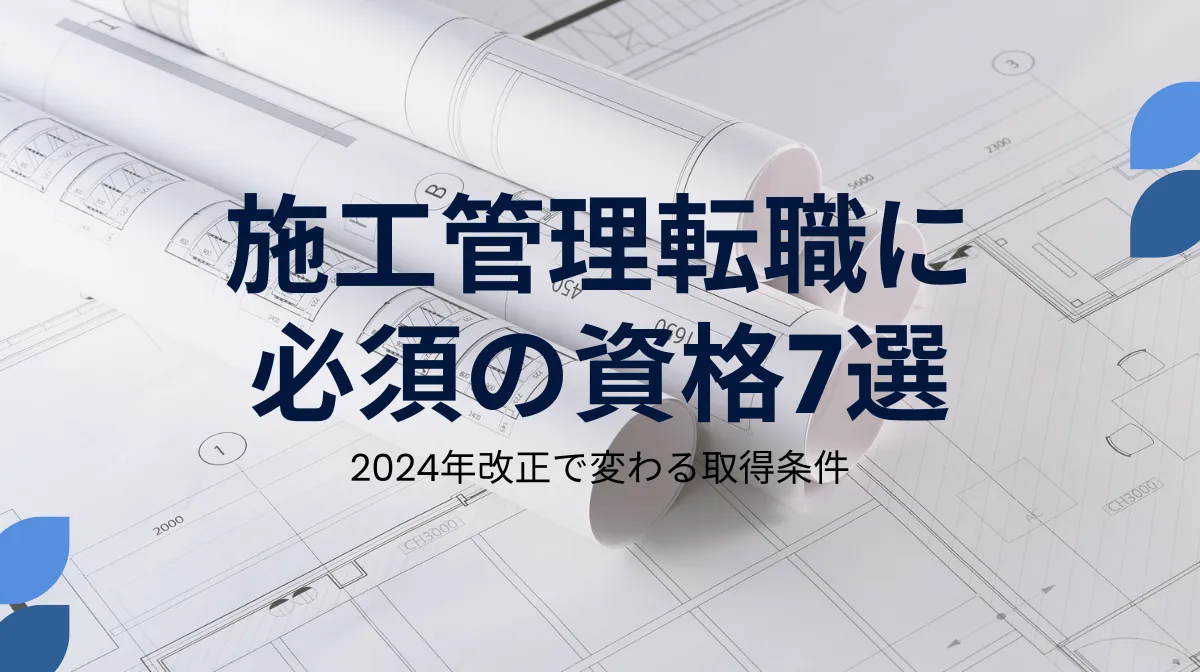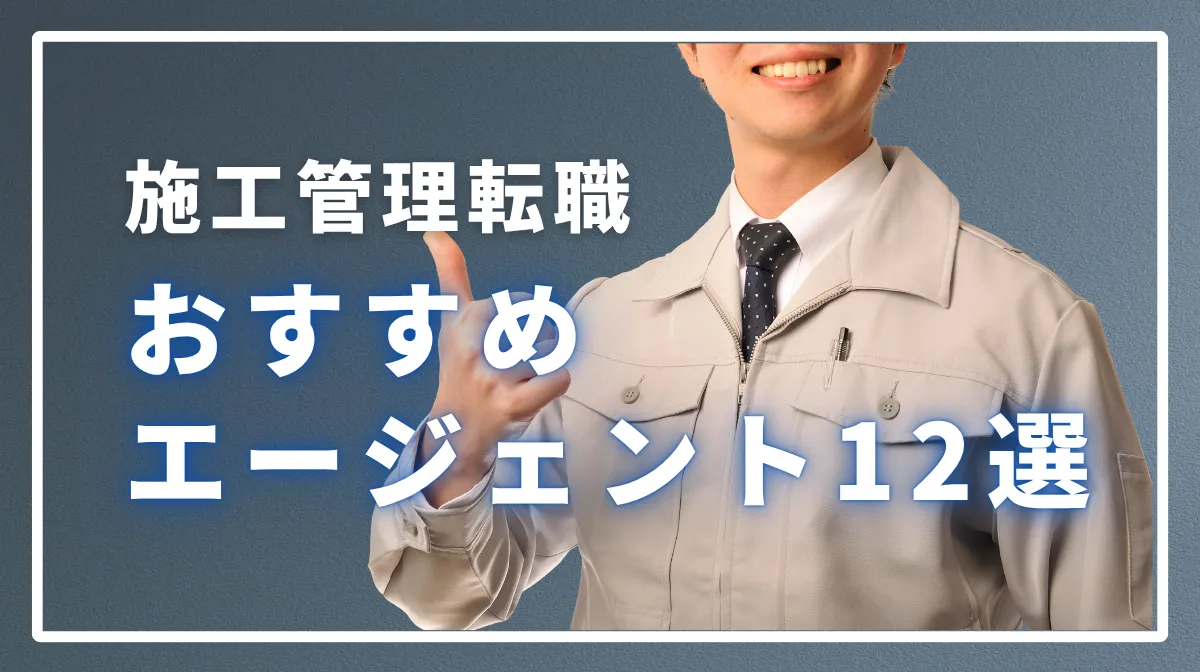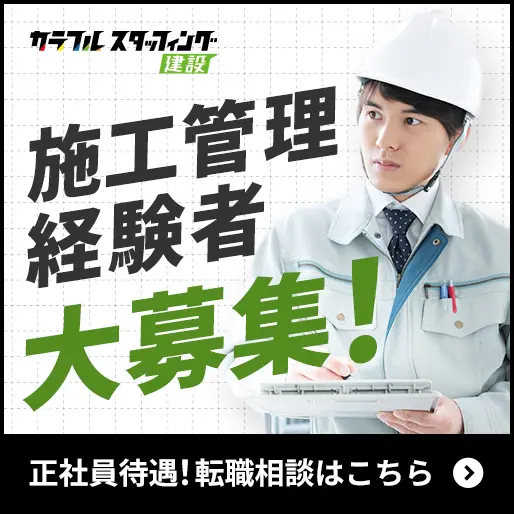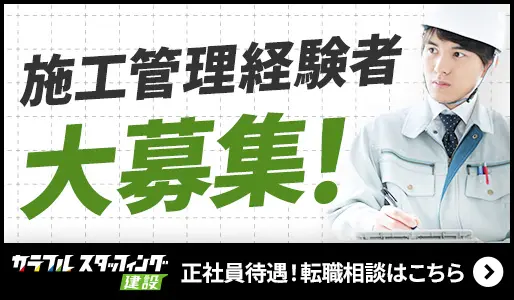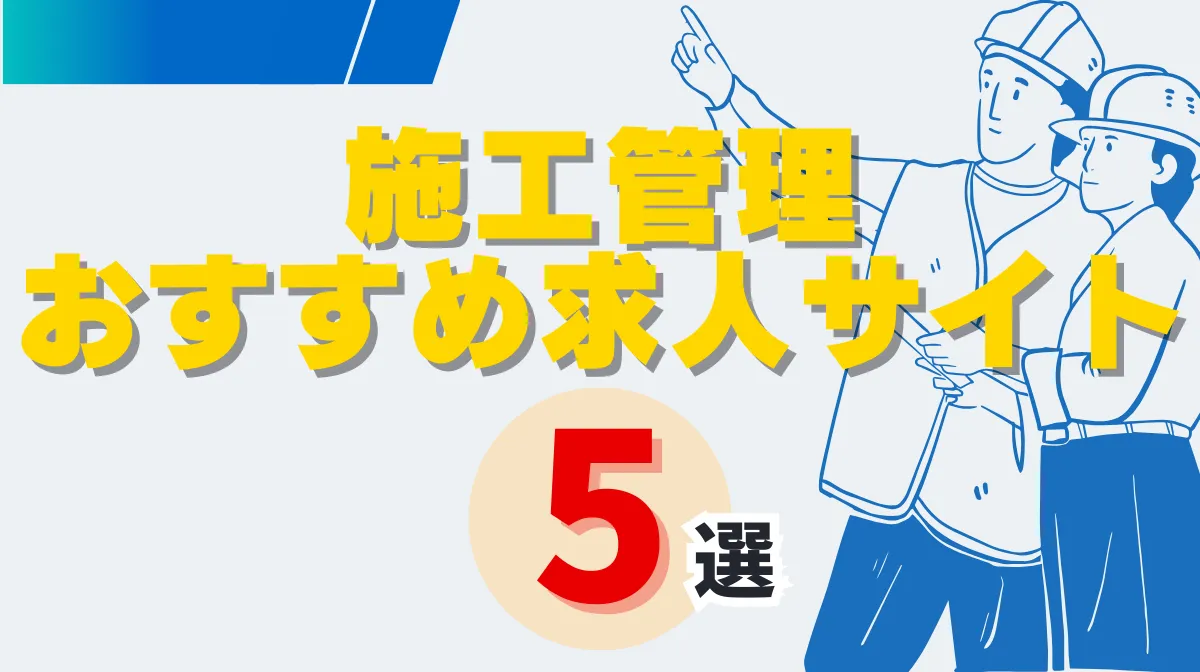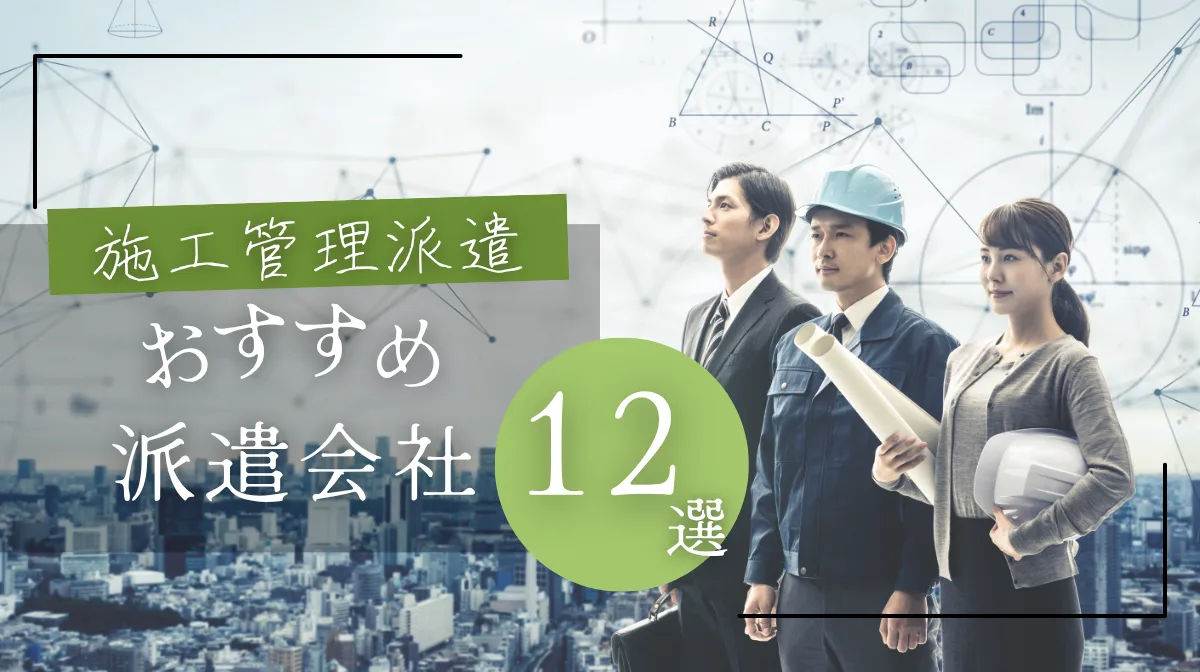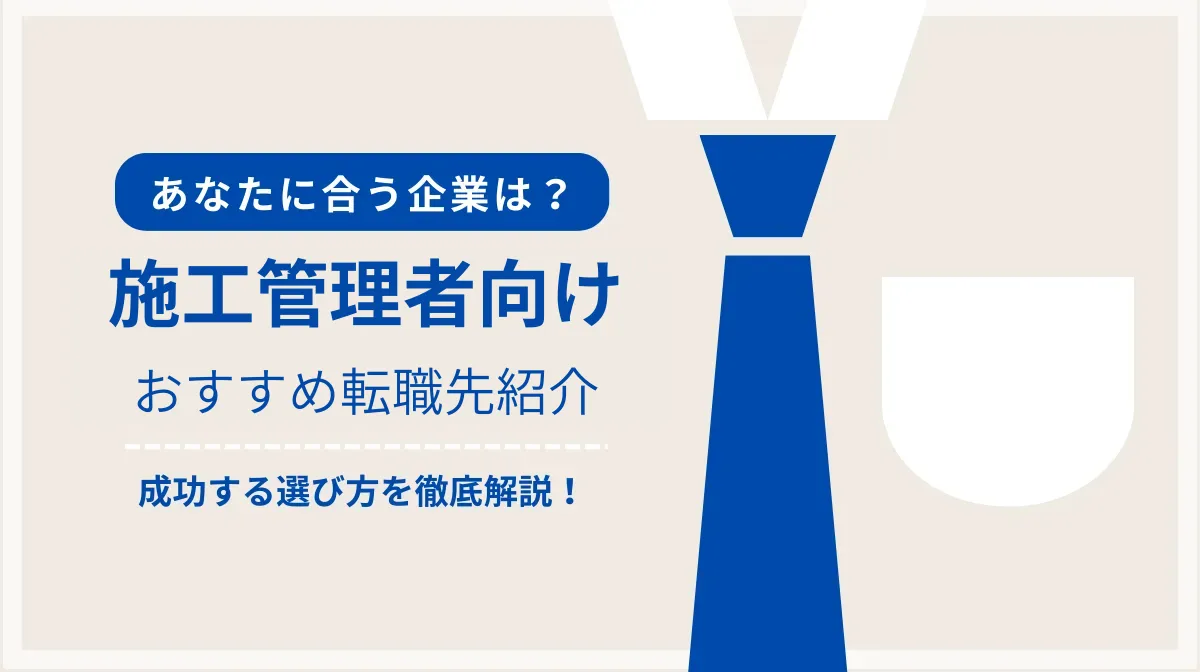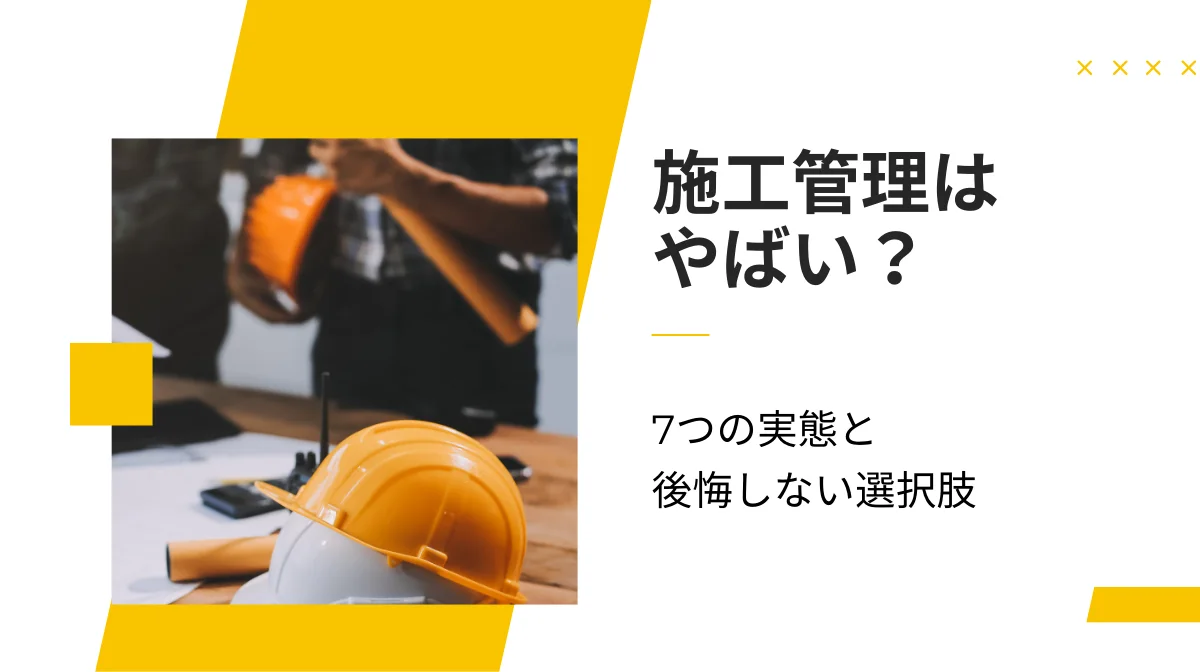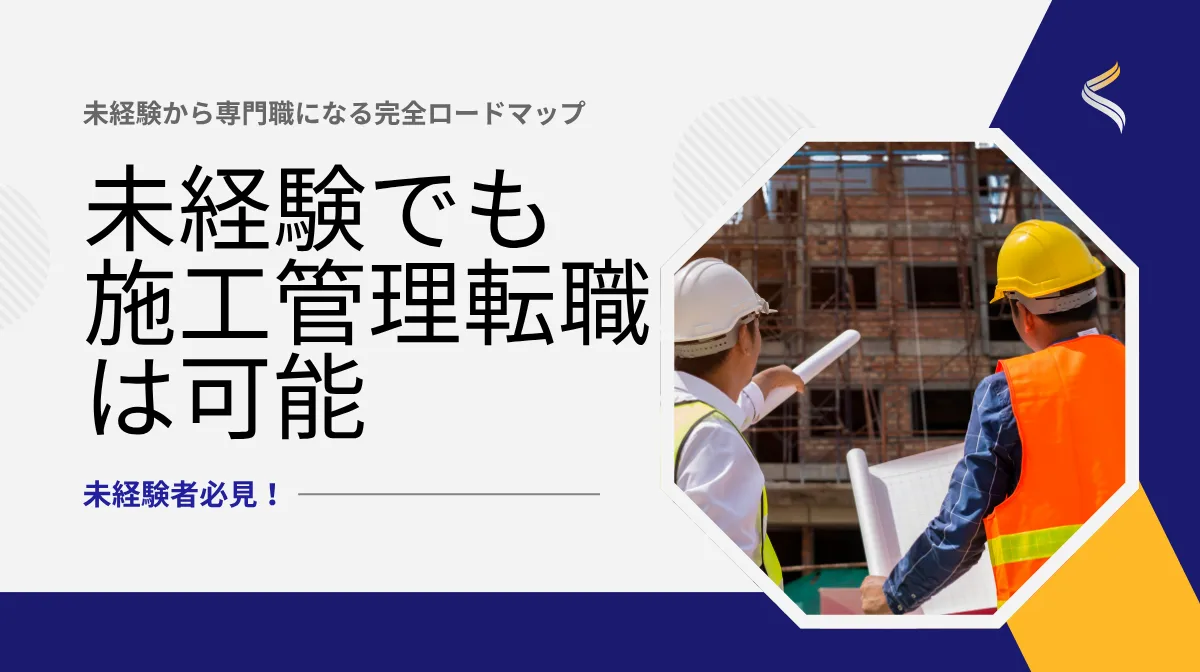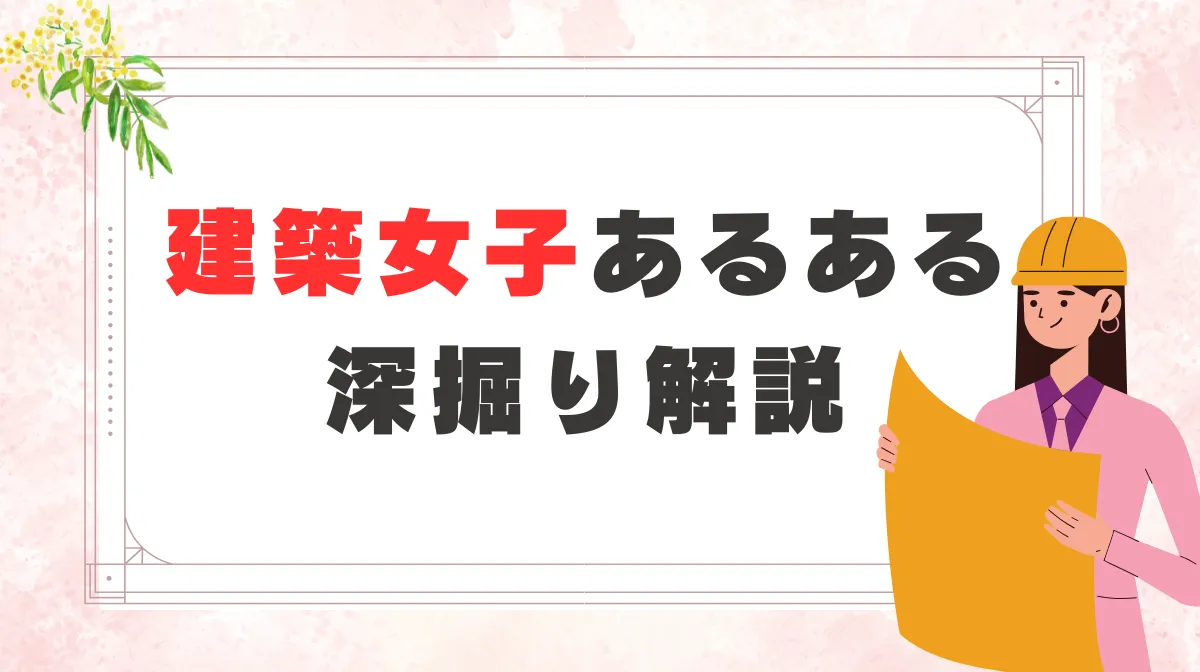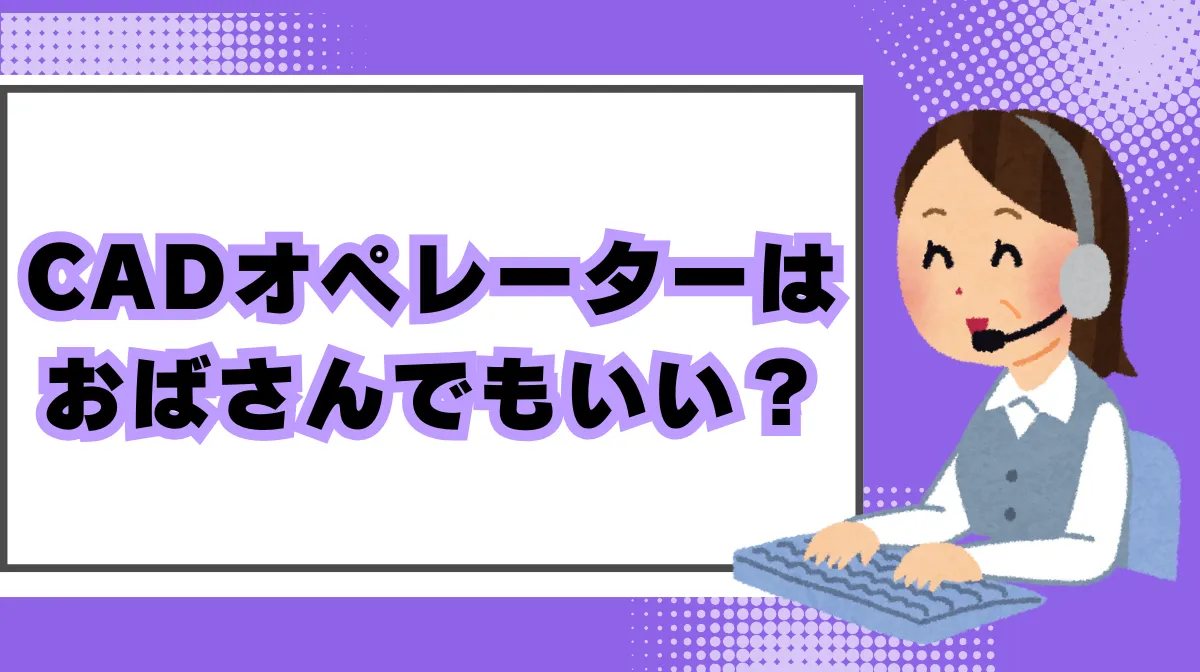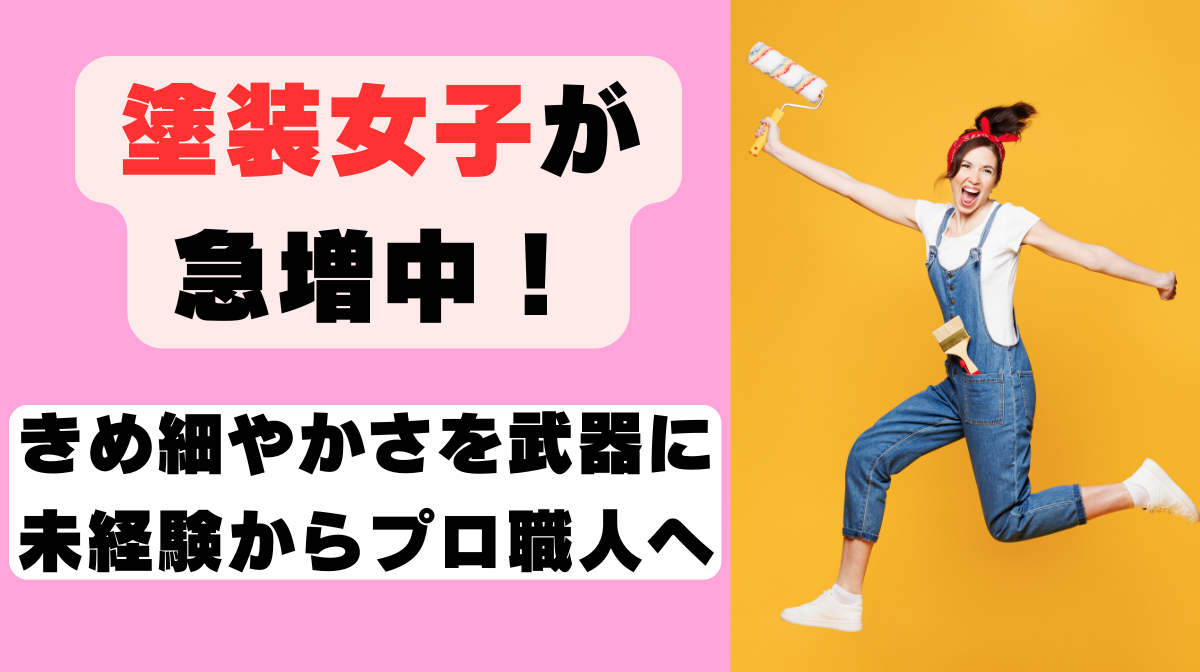1級管工事施工管理技士は、大規模設備工事で監理技術者として活躍できる国家資格です。
2024年の制度改正により受験資格が大幅に緩和され、19歳以上なら第一次検定を実務経験なしで受験可能となりました。
合格率は第一次検定40%、第二次検定60%と決して易しくありませんが、年収アップや転職市場での高評価など大きなメリットがあります。
【多様な現場経験で市場価値を高めたい施工管理者の方へ】
施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。
正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。
20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。
▼無料・簡単・30秒で完了!
カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる
- 2024年改正後の最新受験資格と試験制度の変更点
- 第一次・第二次検定の合格率と効率的な学習方法
- 資格取得による年収アップと転職市場での評価
1.1級管工事施工管理技士とは

1級管工事施工管理技士は、建設業界において空調設備や給排水設備などの管工事を総合的に管理できる国家資格です。
大規模設備工事では必ず配置が求められる「監理技術者」として、現場を指揮することが可能です。専門性と責任の両面で極めて重要な資格とされています。
近年はインフラの老朽化対策、省エネ設備や再生可能エネルギー関連工事の増加に伴い、管工事需要は右肩上がりです。しかし人材不足が深刻化しており、有資格者の市場価値は今後高まることが予想されます。
結果として、資格取得は将来の安定とキャリアアップに直結する大きな武器となります。
2.1級管工事施工管理技士試験の概要

1級管工事施工管理技士試験は第一次検定と第二次検定の二段階制です。
第一次検定…工学基礎知識や法規を中心とした選択問題
第二次検定…現場経験を基にした記述問題で、総合的な施工マネジメント力を試される
毎年出題傾向が見直されるため、最新情報を把握し計画的に学習することが欠かせません。
受験料
1級管工事施工管理技士の受験料は、2025年度試験から第一次検定・第二次検定ともに12,700円(非課税)に改定され、従来の10,500円から引き上げられました。
申し込みや支払いは検定ごとに行う必要がありますので、早めの準備が必要です。
受験地
試験は全国10都市(札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇)で実施されます。お住まいの地域によっては、遠方の会場で試験を受ける必要があります。
出願前に会場までのアクセスや宿泊計画を立てておくと安心です。
試験範囲
【第一次検定の出題範囲】
機械工学、衛生工学、電気工学、建築学といった管工事に必要な基礎理工系知識に加え、設備、設計図書、施工管理、関連法規など幅広い分野が含まれる
【第二次検定の出題範囲】
第二次検定は記述式で出題され、施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などの実務応用力が問われる
受検者自身の経験と施工知識を、記述表現を通じて論理的にまとめられることが求められる
3.【2024年改正】最新の1級管工事施工管理技士受験資格を解説

2024年の改正により、1級管工事施工管理技士の受験資格はこれまで以上にシンプルかつ柔軟になりました。
学歴や実務経験に関する条件が見直され、「誰もが挑戦しやすい資格」へと一新されています。改正ポイントや新設資格について、具体的に解説します。
なお、2028年までは経過措置期間であり、旧受験資格と新受験資格のどちらで受験するかを選べます。
第一次検定は19歳以上なら実務経験なしでOK
2024年改正により、第一次検定(旧:学科試験)は19歳以上・実務経験なしでも受験可能となりました。
これにより、高校卒業直後や大学在学中でも挑戦でき、若手や異業種からのチャレンジがしやすくなっています。
社会人経験が浅くても資格取得の入り口に立てるようになり、将来のキャリア形成を早期に始めることができます。
さらに、第一次検定合格者は「1級管工事施工管理技士補」として登録できるため、現場で補助的な立場から実務を学びながら経験を積むことが可能です。
この制度は、若年層が働きながらキャリアを積み重ね、第二次検定合格を目指す流れを後押ししています。
参照元:一般財団法人 全国建設研修センター|1級管工事施工管理技術検定
第二次検定に必要な実務経験年数
第二次検定(旧:実地試験)では、これまでは学歴や職歴に応じた実務経験が必要とされ、たとえば4年制大学卒は最長4年6カ月以上、短大・高専・専門学校(専門士)は最長7年6カ月以上、高校・専門学校(専門課程)は最長11年6カ月以上の経験が目安とされてきました。
さらに、2級第二次検定に合格している人は、1級第一次検定に合格すれば、同じ実務経験の条件で1級第二次検定を受験できるようになりました。
参照元:
一般財団法人 全国建設研修センター|旧受験資格
一般財団法人 全国建設研修センター|新受験資格
一般財団法人 全国建設研修センター|新受験資格
新設された「技士補」とは?
2024年改正で新設された「1級管工事施工管理技士補」は、第一次検定に合格すると登録できる新しい区分資格です。
主任技術者や監理技術者の補助として現場に入り、工程管理の一部や施工記録、安全管理の補助などを担います。

合格直後から実務経験を積めるため、第二次検定に必要な実務年数を効率よく満たせるのが最大のメリットです。
履歴書や名刺に記載でき、就職や転職の際にも「専門職を目指している人材」として評価されやすくなります。
▼あわせて読みたい
1級施工管理技士補について詳しく知りたい方は、試験内容や勉強方法を含めた専門記事で詳細をご確認ください。
4.1級管工事施工管理技士の難易度と合格率

1級管工事施工管理技士試験の難易度や合格率は、他の建設系国家資格と比べても高めです。
基礎知識だけでなく、実務での応用力や記述式での表現力も問われるため、十分な準備が欠かせません。
ここでは過去の合格率データや各検定の特徴・対策ポイントを詳しく解説します。
過去の合格率データ
1級管工事施工管理技士試験の合格率は、近年では第一次検定が約40%前後、第二次検定が約60%前後で推移しています。
ただし、第一次検定は年度によって約20%から50%台と大きな幅が見られます。
一般の国家資格と比較して難易度はそれほど高いわけではありませんが、専門分野の知識が多く問われるので、計画を立てて学習に取り組むことが重要です。
合格率に年ごとのばらつきが見られるのは、出題傾向の変化や受験者層の違いが影響しているためです。
特に建設業界では若手不足から社会人経験の浅い受験者が増えており、その背景が数値に表れているとも言えます。
データを鵜呑みにするのではなく、自分に適した学習計画と試験対策を整えることが大切です。
第一次検定の難易度と対策
第一次検定は四肢択一式で、合格率は40%前後と比較的高めですが、範囲が広いため一夜漬けでは太刀打ちできません。
特に「空調・衛生」部門は全体の約20%を占めており配点比重が大きいため、基礎知識の暗記に加えて現場の流れを理解した学習が重要です。効果的な学習ポイントは以下のとおりです。
- 過去問演習
直近5年分を繰り返し解いて出題パターンに慣れ、頻出問題を確実に得点源にする - 計算・図表対策
電気設備や空調計算、配管に関する数式は理解不足だと大きな失点につながるため、苦手意識を持たず繰り返し訓練する - 法規・最新知識
建設業法や労働安全衛生法などは毎年改正があるため要注意
特に近年は「省エネ・カーボンニュートラル・環境配慮技術」に関する出題が増加傾向にある
暗記だけでなく、施工現場の映像や実際の作業を思い描きながら学習することで、知識が長期的に記憶に残り、第二次検定の準備にもつながります。
第二次検定の難易度と対策
第二次検定は、合格率60%前後です。問題は記述式で構成され、工事計画の立案、安全・品質管理、トラブル時の判断など、実務に即した対応力が求められます。
さらに2024年以降は、出題形式が大きく見直され、経験記述の設問が廃止されました。

その代わりに、工程管理・安全管理の設問が必須化され、また空調・衛生に関する選択問題で、経験で得た知識や実務的な知見を幅広い視点から確認する内容に改められています。
これにより、単なる経験談ではなく、より体系的で実践的な施工マネジメント力が試されるようになりました。
合格のためのポイントは以下の通りです。
- 知識の整理
過去の工事事例やトラブル対応の経験を棚卸しし、施工管理上の知識と結びつけて理解しておく - 論理的な記述練習
暗記した模範解答を再現するのではなく、自分の言葉で根拠を持って説明できるよう訓練する
文章構成力や論理性が評価される - 過去問・演習の活用
新しい形式に沿った問題演習を繰り返し、制限時間内で的確に答案をまとめる練習が不可欠
実務経験が浅い人でも、アウトプット練習を重ねることで十分合格は狙えます。
むしろ経験に頼りすぎると論点が外れやすいため、「現場経験+過去問演習で整理」の組み合わせが有効な学習法です。
5.1級管工事施工管理技士資格を取得する3つのメリット
資格を取得する3つのメリット
年収アップが見込める
「監理技術者」として大規模工事に携われる
企業評価(経営事項審査)が上がり貢献できる
1級管工事施工管理技士の資格取得は、単なるスキルアップに留まらず、キャリアや収入面で大きな飛躍をもたらします。
資格を持つことで、現場での専門的な管理能力が認められ、監理技術者として大規模工事に関わるチャンスが増えるほか、企業からの評価も高まり経営事項審査においても有利に働きます。
これらのメリットは転職市場でも強い武器となり、長期的なキャリア形成や安定した収入アップを実現するための重要なステップです。以下で具体的に3つのメリットについて詳しく解説します。
①年収アップが見込める
国税庁が公開している2023年の民間給与実態調査によると、給与所得者全体の平均給与は460万円です。
「求人ボックス」の給与ナビによると、管工事施工管理技士の平均給与は572万円(2025年4月現在)でした。
単純比較はできませんが、管工事施工管理技士の平均給与は、給与所得者全体の平均給与を100万円ほど上回っています。
企業によっては資格手当が用意されていたり、より複雑なプロジェクトや大規模な管工事の管理を任される場面が増えたりするため、それらが収入に反映されると予想されます。
各種求人情報を見ても、2級管工事施工管理技士より1級管工事施工管理技士の方が、想定年収のレンジが高く設定されています。
中には800万円〜1,000万円といった高年収の募集例もあり、1級取得が年収アップにつながることがわかります。
「主任技術者」から「監理技術者」への成長がダイレクトに評価・報酬アップに結びつきやすいのが大きな魅力です。
参照元:
国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査
求人ボックス|管工事施工管理技士関連の仕事の平均年収は572万円/平均時給は1,204円!給料ナビで詳しく紹介
②「監理技術者」として大規模工事に携われる
1級管工事施工管理技士の資格を取得すると、法的に認められた「監理技術者」として、大規模な公共工事や数億円規模の民間プロジェクトに携わることが可能です。
監理技術者は工事全体の管理責任者として、安全管理や工程管理、品質保証など多岐にわたる役割を担います。
そのため、現場における責任と影響力は非常に大きく、技術者としてのキャリアは飛躍的に広がります。

さらに、監理技術者の資格を持つことで、企業内での評価や信頼も高まり、マネジメント層への昇進や重要プロジェクトへの抜擢など、活躍の場が格段に増えるはずです。
これにより、単なる現場監督を超えた高度な技術者としての専門性とリーダーシップを発揮できます。
③企業評価(経営事項審査)が上がり貢献できる
建設業界で重要視される「経営事項審査(経審)」において、1級管工事施工管理技士の有資格者は、企業の技術力を示す重要な評価対象です。
資格保有者の数や質が経審の評価点に直結し、これにより企業は公共工事の受注競争で有利な立場を獲得します。
また、信用力の向上によって金融機関からの借り入れ条件が良くなり、資金調達もスムーズに行えるようになります。
結果として、会社全体の経営基盤を強化する役割を果たし、現場だけでなく経営層や顧客からも重宝される人材として認識されます。
1級技術者はこのように、企業の成長と発展に直接貢献できる重要な存在として期待されています。
▼あわせて読みたい
施工管理全体の年収相場や地域別データ、年収1000万円を実現する具体的な方法について詳しく解説しています。
■1社では経験できない圧倒的な成長を求める施工管理者の方へ
施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。
正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。
▼無料・簡単・30秒で完了!
カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる
6.1級管工事施工管理技士と2級の具体的な違い

1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士は、どちらも管工事分野における現場管理のプロフェッショナルとして認められる国家資格ですが、その役割や業務範囲、受験資格にははっきりとした違いがあります。
特に1級は大規模かつ重要な現場で求められる資格であり、職域やキャリアの幅、転職市場での価値も大きく異なります。
自身のキャリアプランにあわせて、どちらの資格を目指すべきか早い段階で目標を定めることが重要です。
以下では、業務範囲、受験資格、そして転職市場におけるそれぞれの評価について詳しく解説します。
業務範囲の違い
| 1級管工事施工管理技士 | 2級管工事施工管理技士 | |
|---|---|---|
| 工事規模 | 制限なし | 中小規模のみ |
| 主任技術者 | 従事可能 | 従事可能 |
| 監理技術者 | 従事可能 | 従事不可 |
| 大規模公共工事 | 対応可能 | 対応不可 |
| 責任・ポジション | 重責・管理職候補 | 現場レベル |
1級は大規模工事や公共性の高いプロジェクトを含む、すべての管工事の現場で主任技術者、監理技術者として従事できます。
一方、2級は担当できる工事規模に上限があります。2級は主に中小規模の現場や特定の条件下での主任技術者に限られます。
1級の資格保持者はより責任の重い役割やマネジメントポジションにも就くことができ、多様なプロジェクトへ参画できます。
2級では経験できない大規模案件や社内での重要ポジションを担えるのが1級の大きな魅力です。
また、法令上で求められる技術者配置要件の対応範囲にも大きな差が生まれます。特定建設業者が請け負う大規模工事における技術者配置要件では、1級保持者のみが務められる役割です。
受験資格の違い
2級管工事施工管理技士は、受験に必要な学歴や実務経験の条件が比較的緩やかに設定されています。
高卒者や実務経験の浅い方でもチャレンジしやすい構造になっているため、より多くの人に資格取得のチャンスがあります。
一方、1級は受験資格がより厳格で、第二次検定に進むには学歴や職歴に応じた一定以上の実務経験年数を満たす必要があります。
さらに2024年改正後は、第一次検定については年齢要件のみで受験可能となったものの、最終的な1級資格取得には現場経験が不可欠です。
このため、自身のキャリアと計画的に資格取得の進路を選択することが求められます。
転職市場での評価の違い
転職市場では、1級管工事施工管理技士の資格は「即戦力」として高い評価を受けます。
これにより、一般社員としてのポジションに留まらず、係長・課長クラスといった管理職候補としての採用につながるケースも少なくありません。
一方、2級資格も一定の評価は得られるものの、担当できる工事規模や責任範囲が限定的であるため、転職市場での年収アップやポジションの幅はどうしても限られます。
結果として「より待遇を上げたい」「大手・官公庁案件に関わりたい」と考える人にとっては、1級資格の有無が採用段階で明確な差となって表れます。
このように、職域やキャリア選択の自由度という観点から見ても、2級は入口、1級はキャリアの飛躍台と捉えられます。自身の市場価値を高めたい人にとって、1級は確実に強力な武器となります。
7.1級管工事施工管理技士試験合格に向けた効率的な勉強法
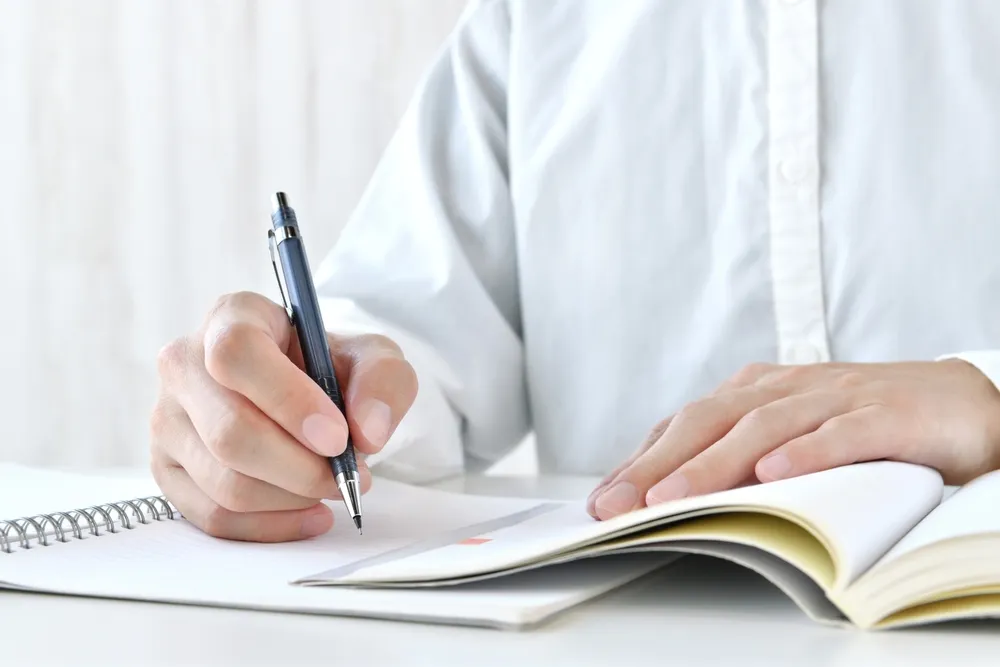
1級管工事施工管理技士試験を突破するには、効率的な学習計画を立て、自分自身に合った勉強法を採用することが不可欠です。
試験は第一次検定と第二次検定の2段階に分かれており、それぞれ問われる知識やスキルが異なります。
短期間で効果的に理解を深め、合格を目指すためには、過去問の徹底分析や出題傾向の把握、現場経験を活かしたアウトプットの積み重ねが重要です。
忙しい社会人も多い受験者層だからこそ、限られた時間を最大限に活かす学習工夫が求められます。
以下では、第一次検定・第二次検定それぞれの学習のポイントと、自分に合った学習スタイルの選び方について詳しく解説します。
第一次検定のポイント
第一次検定は主に選択式問題で、幅広い分野から基礎知識が問われるのが特徴です。
知識を丸暗記するだけでは不十分です。図表や計算問題、施工管理の基本など総合力が必要となるため、毎日コツコツ継続して勉強する必要があります。
最近の出題傾向の変化にも対応できるよう、最新の教材や問題集を活用するのがおすすめです。また、不明点や苦手分野は早めに克服できるよう、計画的に復習のための時間も取り分けましょう。
第二次検定のポイント
第二次検定では、記述式問題や現場経験に基づく課題が中心です。自分の工事経験を棚卸しし、具体的な事例を交えながら論理的に説明できる力が求められます。
実務に即した課題を想定し、過去の業務や現場でのトラブル対応などを整理しておくと、応用力が身につきます。
現役合格者の体験談や解説書を参考に、答案作成に必要な論述力やマネジメント視点も養いましょう。
自分に合った学習方法の見つけ方
当然のことながら、勉強法は人によって最適解が異なります。自分の性格や生活リズム、現場経験を考慮して勉強スタイルを選びましょう。
独学が得意な人は市販の教材や過去問で計画的に学べますが、苦手分野の克服や疑問点の解消が難しいと感じる場合は、通信講座やオンライン学習サービスの利用もおすすめです。
同じ目標を持つ仲間と情報交換したり、勉強会に参加したりすることはモチベーション維持にもつながります。
忙しい社会人でも無理なく続けられるよう、短期集中型やスキマ時間の活用、スマホ学習など工夫して取り組むことが合格率アップのポイントです。
▼あわせて読みたい
施工管理転職で有利になる資格を総合的に比較検討したい方は、こちらで年収アップにつながる資格選びのコツを解説しています。
8.1級管工事施工管理技士資格取得後のキャリアパスと転職
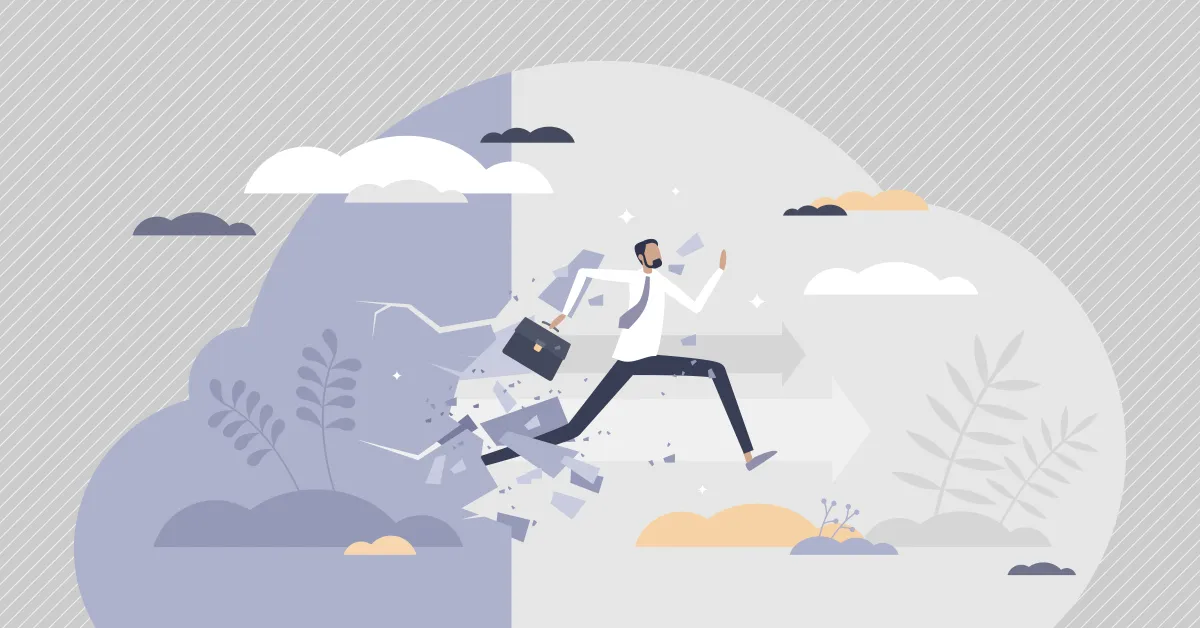
1級管工事施工管理技士を取得すると、キャリアの幅は施工管理にとどまらず大きく広がります。
現場監督や管理業務はもちろん、企画・設計・監査業務への参画やマネジメント層へのステップアップが期待できます。
さらに、官公庁や公共インフラ関連、設計事務所、不動産デベロッパーなど、民間・公共双方の多様なフィールドで活躍のチャンスが生まれます。
将来的には独立やコンサルタント業、教育研修の分野に進むことも可能です。自分の専門性を軸に幅広いキャリアパスを描けるのがこの資格の大きな魅力です。
広がる転職先の選択肢
1級資格を有することで、応募できる求人の範囲が飛躍的に拡大します。

ゼネコンやサブコンといった施工主体の企業だけでなく、設備系の設計事務所や不動産開発企業、官公庁・公共団体など幅広い業種で評価されます。
また、施工現場一辺倒ではなく、プロジェクト管理、品質保証、積算、設備計画など、オフィスワーク寄りの業務に関わることも可能です。
異業種とコラボレーションする再開発案件や環境配慮型プロジェクトにも関われるため、キャリアは現場監督から都市開発や街づくりへと広げることも十分可能です。
施工管理以外のキャリアも可能に
1級を活かせる仕事は施工管理だけではありません。例えば、品質管理、メンテナンス管理、営業技術職など、工事の枠を超えたポジションで力を発揮できます。
また、社員育成や研修、社内の技術承継を担う教育担当者としてのニーズも増加中です。
最近では働き方改革が進み、週休制度の改善や時短勤務、テレワークの導入などで柔軟な働き方が広がっています。
そのため、資格を活かしつつワークライフバランスを重視したキャリア設計も可能になってきています。家庭との両立、副業やコンサル的活動など新しい挑戦も視野に入れられます。
資格を武器に有利な転職を実現する方法
資格を持っていても、その価値を最大化できるかどうかは転職活動の戦略次第です。
建設業界に強い転職エージェントを活用すれば、求人紹介だけでなく年収交渉や面接対策まで受けられ、効率的にキャリアを前進させられます。
特に1級有資格者は企業からのスカウトも増えるため、自身の職務経歴書やスキルシートを常に更新しておくことが重要です。
面接では「資格を取った動機」や「これまでの現場でどのように成果を出したか」を具体的な数字や事例と共に語ると強い説得力を持ちます。
また、資格によって将来どう貢献できるか、例えば大規模案件でのリーダー経験、組織の安全体制強化への貢献などを明確に説明できれば、採用担当者に強く印象づけられます。
さらに、LinkedInなどのビジネス向けSNSで業界知見を発信することも有効です。業界とのつながりを広げながら、思わぬオファーにつながる可能性もあります。▼あわせて読みたい
1級資格を活かした転職を成功させるには、建設業界に特化した転職エージェントの活用が効果的です。選び方のポイントも解説。
9.1級管工事施工管理技士を取得してキャリアアップ
1級管工事施工管理技士は建設業界でのキャリアアップに欠かせない重要な資格です。
2024年の制度改正により若手でも挑戦しやすくなり、合格すれば監理技術者として大規模工事に携われます。
年収アップや転職市場での高評価が期待でき、施工管理以外の分野への展開も可能です。計画的な学習と継続的な努力で、確実に合格を目指しましょう。
■多様な現場経験で市場価値を高めたい施工管理者の方へ
施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。
正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。
▼無料・簡単・30秒で完了!
カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる